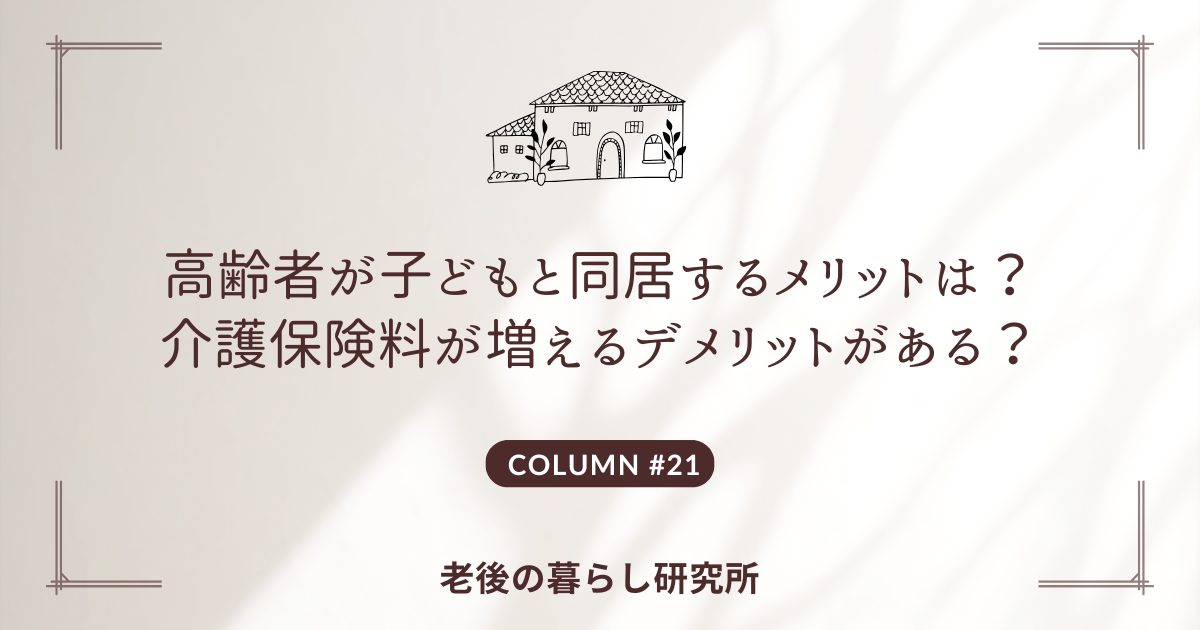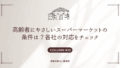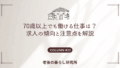年齢を重ねると、自分1人または夫婦2人での生活が難しくなることがあります。
とくに、持病があったり身体が自由に動かなくなったりする場合には、頼りになる誰かに居てほしいと思うことは珍しくありません。
そこで今回は、高齢者が子どもと同居するメリットのほか、同居前に知っておきたいデメリットを解説します。
子どもとの同居を考えるきっかけ
自由に動けなくなったら、子どもと同居したいんだけど…
親のきっかけと子どものきっかけ、それぞれを見てみるワン!
- 自分に介護が必要になった
- 自分に日常生活のサポートが必要になった
- 育休が終わり子どもの面倒を見られなくなった
- 将来を考えて購入するマイホームを二世帯住宅にした
親に介護が必要になった
親側が子どもとの同居を考えるきっかけとして挙げられるのが、自分に介護が必要になったことです。
具体的には、以下のような理由から介護が必要になります。
- 認知症が進んだ
- 脳卒中でまひが残った
- 足のむくみで立てなくなった
- 転んで骨折した
自分に日常生活のサポートが必要になった
介護ほど本格的な支援ではなく、日常生活でサポートが必要になり、親から子どもへ同居を打診する場合があります。
具体的には、以下のような理由からサポートが必要になります。
- 年金額が少なく生活費が足りなくなった
- 免許返納して通院が難しくなった
- 年齢とともに漠然とした不安が大きくなった
子ども夫婦の育休が終わり子どもの面倒を見られなくなった
子ども夫婦が共働きの場合、子どもの面倒を見てもらえることを期待して、親と同居することがあります。
共働きをしている方は、保育園に子どもをかよわせながら家庭と仕事を両立させています。
しかし、子どもが体調不良になった場合、仕事を休んだり遅刻したりしなくてはなりません。
業務内容や役職によっては、自分が休むと同僚に迷惑をかけてしまうと考えるでしょう。
キャリアアップを目指し仕事を頑張っている子育て夫婦の場合、自分たちの代わりに子どもの面倒を見てもらうために、親との同居を希望することは珍しくありません。
親側も孫の面倒を見ることが苦ではないならば、お互いにメリットがあるといえるでしょう。
子どもが将来を考えて購入するマイホームを二世帯住宅にした
とくに長男に多い考え方ですが、自分が将来的に親の面倒を見なければならないと思うことがあります。
こうした考えを持つ子どもの場合、夫婦で購入するマイホームを二世帯住宅にして、親を招きたいと考えます。
また、マイホームを購入したくても資金が不足している場合、親からの資金提供を受ける代わりに二世帯住宅にすることもあるでしょう。
子どもと同居するメリット
一緒に住める心強さが一番のメリットよね
ほかにもたくさんメリットがあるから、自分にとって魅力的なものがいくつあるか見てみるワン!
- 体調不良のときに助けてもらえる
- 手の届かないところ・力仕事をしてもらえる
- 孫とすぐ会える
- 料理を作ってもらえる
- 車で送迎してもらえる
- 話し相手になってもらえる
- 一人暮らしの不安がなくなる
体調不良のときに助けてもらえる
年齢を重ねて高齢になると、若い頃と比較して体調不良になることが増えるのが一般的です。
体力がない高齢者が体調不良になると、1人で通院できないのはもちろんのこと、食事や掃除などの日常生活にも支障が出ます。
手の届かないところ・力仕事をしてもらえる
体力や筋力がなくなってくると、若い頃はできていた作業ができなくなることがあります。
子どもと同居していれば、以下のような作業をサポートしてもらえます。
- 電球の交換
- 風呂掃除
- 庭木の枝切り
- 雑草むしり
- 布団干し
孫とすぐ会える
同居する子どもに子ども(自分から見て孫)がいる場合、可愛い孫にすぐ会えることがメリットです。
どのようなタイプの家で同居するかによりますが、リビングルームを共有するタイプの二世帯住宅ならば、毎日食事の時間などで顔を合わせられます。
料理を作ってもらえる
高齢になると、自分で食材を購入して料理する機会が減るのが一般的です。
お弁当やお惣菜に頼る生活だと、高血圧・高血糖が悪化するリスクがあります。
子どもと同居すれば、自分のぶんも料理してもらえることがメリットです。
単に料理が面倒になるほか、さまざまな要因が考えられます。
- 長時間台所に立つことができない
- 食材を購入する交通手段・持ち帰る体力がない
- 味覚が鈍くなり味付けが苦手になった
車で送迎してもらえる
足腰が弱くなり長距離を歩けなくなった方の場合、買い物にいくことが困難になります。
また、今まで車を運転していた方であれば、免許返納しでかける気力を失うことがあります。
こうした行動範囲の変化は、体力低下にもつながり老化を早めるリスクにもなります。
子どもと同居している場合だと、車で送迎してもらえることがメリットです。
子どもと一緒に買い物にいけば気分転換になるほか、自然と歩数が多くなり健康増進効果が期待できます。
話し相手になってもらえる
子どもと同居した場合、毎日何らかのコミュニケーションを取れることがメリットです。
とくに、朝食または夕食を一緒に食べる方は、話し相手になってもらえるメリットがあります。
一人暮らしをしている高齢者の多くは、身近に気軽に話せる友人がいません。
しかし、子どもと同居していれば、ちょっとしたおしゃべりができてストレス解消になります。
一人暮らしの不安がなくなる
50~60代では自由を満喫していても、70代後半になると加齢によりさまざまな不安が発生します。
こうした不安は、子どもと同居すれば解消できる不安がほとんどです。
- 病気になることが多くなった
- 身体の自由がきかなくなってきた
- 足腰が弱り掃除ができなくなった
- 倒れても誰にも見つけてもらえないかもしれない
子どもと同居するデメリット
デメリット?私には無関係ね
実は、暮らし始めてから気がつくデメリットも多いワン!
- 顔を合わせることがストレスになる
- 嫁姑問題が発生する
- 孫の教育方針の違いからケンカになる
- 介護保険料・介護保険の利用料金が増える
- 生活費が増える
- ほかの子どもとの間で相続問題が発生する
顔を合わせることがストレスになる
今までは離れて暮らしていた子どもと同居する場合、顔を合わせること・話すこと・キッチンや浴室を共有することなどにストレスを感じることがあります。
世代が違えば価値観も違うので、生活のあらゆる場面で気に入らないことがあるでしょう。
場合によっては、顔を合わせたくないと感じられるほどストレスになることがデメリットです。
嫁姑問題が発生する
息子と同居する方に多いのが、嫁姑問題が発生するといったデメリットです。
とくに、娘がいない男の子兄弟のみを育てた母親は、最近の若い女性の感覚を知らないことがあります。
離れて暮らしている分には問題がなくても、一緒に暮らし始めると我慢できないほどの問題に発展することは珍しくありません。
孫の教育方針の違いからケンカになる
共働きの子ども夫婦に代わり孫の面倒を見ている方の場合、孫の教育方針に口を出してしまい、ケンカになりやすいことがデメリットです。
孫の面倒を見ているから孫の教育について決定権があると思われるかもしれませんが、子ども夫婦はそう考えないことに注意が必要です。
どこまで子育てを手伝うか線引きし、求められた場合にアドバイスをすると良いでしょう。
もちろん、孫が生活のすべてにならないよう、自分の趣味の時間を確保することも大切です。
介護保険料・介護保険の利用料金が増える
子どもと同居しているだけでなく、同一世帯として生活している場合、親側の介護保険料や介護保険の利用料自己負担分が増える可能性があることがデメリットです。
同一世帯とは、住所が同じかつ家計が同じであることが条件です。
同一世帯は、同じ住民票に氏名が記載されています。
親世帯と子ども世帯で生計を別にしているならば、住民票をわけるための世帯分離手続きが必要です。
増える可能性があるのは、介護保険料・高額介護サービス費です。
どちらも世帯年収によって料金に差があり、住民税非課税の親ならば世帯分離で負担を減らせます。
生活費が増える
自分が長く暮らしていた家に子どもを呼び寄せて同居する場合、生活費を折半するのが一般的です。
しかし、隠れた生活費が折半しきれず、自分の費用負担が増えることがデメリットです。
食費と日用品にかかる費用を大まかに折半した場合、水道・電気・ガスといった光熱費が漏れている場合があります。
今まで一人暮らしをしていた方が子ども夫婦と孫など複数の家族と同居する場合、水道光熱費が跳ね上がる可能性があります。
子どもと同居を始めるタイミングで毎月いくらもらうか計算することが大切です。
ほかの子どもとの間で相続問題が発生する
同居する子ども以外に子どもがいる場合、相続問題が発生しやすいことがデメリットです。
とくに、同居している不動産が主な財産である場合、公平な相続が難しくなります。
同居している子どもはすでに住んでいる家だという理由から、不動産を1人で相続することを主張するかもしれません。
公平な相続のためには、不動産のほかに預貯金や有価証券を残すことが解決策になります。
自分の死後に子ども同士の相続問題が発生しそうだと感じたら、公正証書遺言の作成や遺言執行者の指定などを検討してみましょう。
まとめ
病気や体力低下など、高齢になると子どもとの同居を希望することがあります。
子どもと同居した場合、すぐに助けてもらえるほか話し相手になってもらえることなどがメリットです。
ただし、一緒の生活をストレスに感じやすいことや介護保険料が増えることなどは子どもとの同居におけるデメリットです。